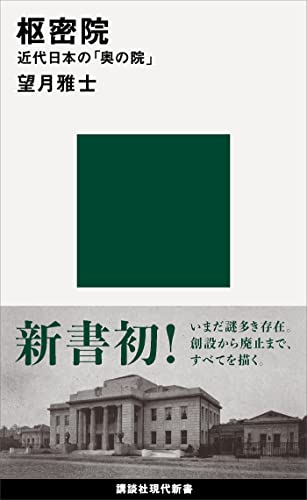2006.03 韓国(ソウルへ、顕忠院、安重根紀念館、板門店、ロッテワールド、帰国)
2007.08 中国(上海へ、南京へ、南京、泰山へ、泰山、北京へ、天安門、抗日紀念館、長城、済南へ、済南、上海豫園、上海外灘、帰国)
2008.01 欧州(アムステルダムへ、アムステルダム、ブリュッセル、パリ、リスボンへ、ロカ岬、リスボン郊外、スキポール、帰国)
2009.09 韓国&竹島(ソウル、ムクホ、竹島、鬱陵島、独島博物館、良洞マウル、慶州、白村江、ソウル、帰国)
2010.08 イラン(中東へ、 ドーハとイラン入国、 イスファハーンへ、イスファハーン、シーラーズ、ペルセポリス、テヘラン、帰国)
2011.10 東欧(クラクフへ、アウシュビッツ、クラクフ、ワルシャワ、スターリンワールド、ヴィリニュス、ウィーン、帰国)
2012.08 トルコ(イスタンブールへ、イスタンブール、エフェソス、パムッカレ、パムッカレ発、北キプロス、南北キプロス、アダナ、カッパドキア、カッパドキア気球、ボスポラス海峡、イスタンブール、帰国)
2013.07 ロシア(アブダビ空港、 モスクワへ、モスクワ、キジ島、エルミタージュ、ノヴゴロド、サンクトペテルブルク、帰国)
2015.08 バリ(バリへ、クタ、タマンアユン、ブサキ寺院、帰国)
2016.03 タイ(バンコクへ、バンコク、アユタヤ、週末市場、帰国)
2016.11 ソウル(朴槿恵退陣デモ、水原と大規模デモ、慰安婦像)
2017.06 中朝国境(大連、丹東から見る北朝鮮、旅順、帰国)
2018.04 豪州(シドニー、ブルーマウンテンズ、ハンターバレー、帰国)
2018.09 キューバ(ハバナへ、ハバナ、ゲバラ、ビニャーレス渓谷、コヒマル、ビーチ、メキシコシティ)
2019.07〜08 バハマ&アトランタ(バハマへ、ビーチ、ダウンタウン、フラミンゴ、アトランティス、アトランタへ、CNN、MLB、ミッドタウン、居住区、地域図書館、帰国)
当ブログ内の旅行記を探しやすいように、一覧を作りました。時系列に並んでいます。
こうしてみると、ちょっとした歴史を感じますね。これからもどうぞ宜しくお願いいたします。
※旅行記は随時追加しています